現実と信じていたことへの違和感
朝、顔を洗って、鏡の前に立つ。
そこにはいつもの「自分」がいる。
でも、ときどき思うのだ。
――これ、本当に“自分”なのか?
目の前の“像”は、確かに自分の顔をしている。
しかし、左右が反転し、微妙に動きのズレがある。
私が笑えば、あちらも笑う。でも、どこか違う。
その違和感は、ふとした瞬間に深く刺さる。
現実のようで、現実ではない――そんな奇妙な境界線。
この違和感こそが、現実というものの“あやふやさ”を暴く扉なのかもしれない。
現実とは何か ─ 感覚のフィルターの向こう側
私たちは「現実を見ている」と信じている。
けれど実際は、“脳が再構成した映像”を見ているだけ。
目に入った光は網膜に映り、電気信号に変換され、脳がそれを「これはリンゴ」「これは空」と解釈する。
つまり私たちは、世界そのものを直接見ているわけではない。
見るたびに脳が作り直す“仮想の世界”を、あたかも現実だと信じているのだ。

鏡の像も同じだ。
そこに「本物の私」はいない。ただ、光と反射と脳の解釈が作り出した“像”があるだけ。
それを毎日見つめながら、私たちは「これが自分だ」と信じ込んでいる。
――信じることで、現実は成立している。
だが、信じることをやめた瞬間、現実は崩れはじめる。
他者のまなざし ─ 社会という巨大な鏡
私たちは、自分の顔を直接見ることができない。
だから他人の目、言葉、評価が、自分を知るための“鏡”になる。
SNSの「いいね」も、現代の鏡のひとつだ。
そこには私の表情や言葉が映り、誰かが反応する。
でもそれは、加工された断片であり、真実の全体ではない。

本当の私ではなく、「こう見られたい私」。
その像が、少しずつ現実の私を侵食していく。
そして、いつの間にか「演じること」が生きることになっていく。
“By the mere appearance of the Other, I am put in the position of passing judgment on myself as on an object.”
「他者が存在するというそのことだけで、私は自らを“対象”として見ざるを得なくなる。」
― ジャン=ポール・サルトル『存在と無』(1943年)
サルトルは、この「見られる」という体験を哲学の中心に据えた。
他人が自分を見る瞬間、私たちは“演じる存在”になる。
鏡の中の自分が、まるで誰かに見られているように感じるのは、
他者のまなざしが、私たちの中にすでに“内在している”からだ。
哲学が見た現実の不確かさ
プラトンの「洞窟の比喩」を思い出す。
洞窟の壁に映る影を、囚人たちは“現実”だと信じている。
けれど、影の外にはもっと広い世界がある。
現実とは、知覚によって作られた影のようなものだ。
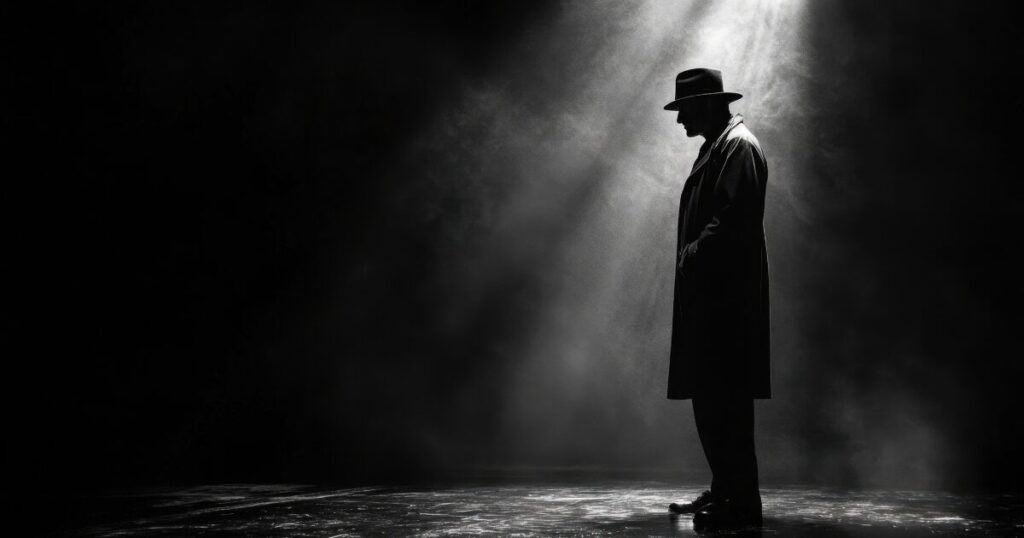
デカルトは、その影の存在すら疑った。
世界のすべてを一度疑い、残ったものはただ一つ――「考えている自分」だけだった。
“Cogito, ergo sum.”
「我思う、ゆえに我あり。」
― ルネ・デカルト『方法序説』(1637年)
感覚も、夢も、他者も疑える。
だが、“思考する自分”だけは疑えない。
この言葉は、世界の不確かさを超えて、「存在の確信」を取り戻すための錨だ。
鏡の中の自分に違和感を覚える瞬間、
私たちはまさに、この“思考する私”と向き合っているのかもしれない。
本当の自分とは何か

ユング心理学では、「ペルソナ(社会的仮面)」と「シャドウ(無意識の影)」という概念がある。
表の顔と裏の顔。どちらも嘘ではなく、どちらも自分の一部。
それを否定せず、両方を認めたとき、ようやく“全体としての私”が現れる。
デカルトは「思考する私」を信じ、
サルトルは「他者のまなざしに揺れる私」を描いた。一方は内なる確信を、もう一方は外からの視線を。
私たちが「本当の自分」を見つけようとするたび、
その間で揺れ動く――内と外、主体と客体、
そして“鏡のこちら側”と“向こう側”の境界線で。
違和感は、目覚めのサイン

たまに感じる、「この現実はどこかおかしい」という感覚。
それは錯覚でも病気でもなく、
“気づき”の始まりかもしれない。
街を歩いていても、誰もが何かに追われているように見える。
同じような服、同じような会話、同じような表情。
だが、その中に一瞬だけ“ノイズ”が混じることがある。
時間がゆがむような感覚。
「ここ、本当に現実なのか?」と感じる一瞬。
違和感を感じるのは、意識が世界の「ひび割れ」に触れた証拠だ。
その小さなひびから、真実の光が差し込むことがある。
現実と仮想、その境界線
夢の中で泣いたことがある。
目覚めても涙は頬を伝っている。
あれは“夢”だったのか? それとも“現実”だったのか?
VRの中で見た夕日も、SNSの中で感じた共感も、
心が動いた時点で、それは“現実”の一部になっているのではないか。

つまり、現実とは「意識が反応した世界」なのだ。物理的か、仮想的かは関係ない。
感情が動けば、それは確かに“そこにあった”。
鏡の中の自分も同じ。
存在していないのに、確かに“感じる”ことができる。
現実と幻の境界線は、思っているよりも薄い。
問いを残す
鏡の中の自分は、本当の自分なのか?
それとも、こちらを見ている“もうひとりの私”なのか?
現実は、信じることで成り立っている。
けれど、その信念が崩れたとき、世界は音もなく形を変える。

だから、違和感を恐れずにいたい。
それは、世界があなたに何かを知らせようとしている合図だから。
そして今日も、鏡の中の誰かが、
微笑みながら――あなたを見ている。
✴️ あとがき(裏の部屋より)
この世界は、あなたが思っているより柔らかい。
触れれば、揺らぐ。
疑えば、形を変える。
信じれば、輪郭を取り戻す。
だから私は、現実を疑うことで、
ようやく「今ここに生きている」と感じるのだ。
参考・出典:
・Jean‑Paul Sartre, L’Être et le Néant(ジャン=ポール・サルトル『存在と無』)— 作品概説(日本語・Wikipedia) https://ja.wikipedia.org/wiki/存在と無
・René Descartes, Discours de la méthode(ルネ・デカルト『方法序説』)— 作品概説(日本語・Wikipedia) https://ja.wikipedia.org/wiki/方法序説
→ 関連記事:月は裏側を見せない ─ 人もまた同じ


